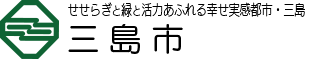(第129号) ~昔の脱穀機~ 千歯扱 (平成11年2月1日号)

現在は機械化が進みコンバインなどで一気に脱穀してしましますが、昔は人力がすべての手扱き作業でした。それでも、これが発明される以前に比べれば、たいへん進歩した便利な道具だったことでしょう。
千歯扱は木製の台木に鉄、竹,木などの葉を櫛【くし】状に並べて固定し、歯と歯のすきまに稲や麦の穂先を差し込んで、手前に強く引っ張って籾を扱き落とす農具です。
歯に鉄が使われるようになったのは江戸初期の元禄年間のことで、和泉高石の大工が発明したという伝えがあります。それより古い次代の千歯扱は竹や木が歯に使われていたと言われます。それにしても江戸時代から明治まで実に長い間、千歯扱は稲の収穫に欠かせない農家の道具として使われ続けてきたものです。
明治末期から大正にかけて、これよりさらに能率のよい回転式の足踏脱穀機が普及し、千歯扱の時代が終わりを告げました。
このように長く、広く全国に普及した農具でしたから、名称にも地方によってさまざまな呼び方があります。
東北地方ではセンコキ、近畿・関東地方ではカナコギ、中部地方ではコバシ・マンガ、南九州ではカナクダと呼ばれているといいます。しかし全国的には、千歯扱(センバコキ)、千歯(センバ)。稲扱(イネコキ)などが、通称のようです。また、地方によっては、ゴケダオシとかゴケゴロシなどの異称もありますが、それは千歯以前の脱穀方法に比べて能率が数段高まったゆえの名称であると思われます。
千歯出現以前の稲扱き道具とは一体どんなものだったのでしょう。
稲作が始まったとされる弥生時代の遺物の「石包丁」が原初の稲扱き道具だったと言われています。手にくくりつけ、稲先だけを扱き、籾を落として収穫する稲刈りの道具でした。
(広報みしま 平成11年2月1日号掲載記事)