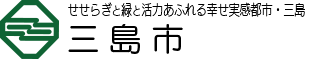(第128号) ~旅の所持品~ 印籠 (平成11年1月1日号)

印籠の原形は中国に始まったと言われます。日本に渡来したころは、印鑑朱肉を入れるための容器だったそうです。それが江戸時代のころになると、印籠の中に応急の薬を入れて腰に提げて持ち歩く旅の必携品として普及しました。
印籠の形には楕円形の二つ重、三つ重、四つ重、五つ重などの各種があり、木製に漆をかけ、蒔絵【まきえ】を施すなどさまざまな意匠を凝らしたものが見られます。一種の工芸品として「粋」を追求し、印籠を単なる形態道具としなかった点に、江戸時代の人々の美学が感じられます。木製のほかに、陶磁器、象牙、金属、竹製などもあります。
こうした印籠の中には、丸薬、散薬、煎じ薬などを分類して入れました。また、入れる薬の違いに気を配り、重ねの合い口に精密な技巧が加えられました。
印籠の左右には緒通しがあり、これに紐を通して緒締めで絞り止め、紐の上端には根付を付け、腰帯に差し込んで持ち歩きました。
さて、薬を入れた印籠を持ち歩かなければならない江戸時代の旅はどのような旅だったのでしょう。
旅の語源説の一つに「他火」とあるように、ひとたび故郷を離れたらそこは未知の世界であり、非日常という緊張感を伴う生活が待っていました。ことに、毎日食べる食事に関しては、他人の火、すなわち自分の家とは異なる竈【かまど】を使って調理をし、食料を確保しなければなりません。また、使う水も故郷と異なる水を飲まなければなりませんでした。つまり、旅先では、常に食中毒のような危険性が隣り合わせにありました。そして、現代のようにどこに行っても薬屋があり、簡単に欲しい薬が手に入るという時代ではありませんから、薬の携帯は欠くことの出来ない旅の要素だったのです。
印籠は昔の東海道の旅を思い起こさせてくれます。
(広報みしま 平成11年1月1日号掲載記事)