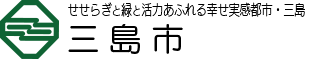ごみ処理広域化の取り組み
経緯
国や県の動向
国は、平成9年(1997年)に都道府県宛てに通知「ごみ処理の広域化計画について」を発出し、ごみ処理に伴うダイオキシン類の排出削減を主な目的として、ごみ処理の広域化を推進しました。
その後、人口減少や3Rの推進などにより、わが国のごみ処理を取り巻く状況が大きく変化したことを受け、平成31年(2019年)には、都道府県宛ての通知「持続可能な適正処理の確保に向けたごみ処理の広域化及びごみ処理施設の集約化について」を発出し、安定的かつ効率的な処理体制の構築を推進するため、都道府県に対し、管内市町村と連携してごみ処理広域化・集約化に係る計画の策定を求めました。
この通知に基づき、静岡県は令和4年(2022年)3月に「静岡県一般廃棄物処理広域化マスタープラン」を策定しました。県マスタープランでは、東部地域ブロック区割りの3市2町(三島市、裾野市、熱海市、長泉町及び函南町)の枠組みが示され、現状に比べ経済面、環境面で効果が高く、当面目指すものとして評価されました。
三島市の取り組み
県マスタープランを受け、三島市を含む3市2町と県は検討を重ね、将来的に人口減少や地球温暖化対策等により、ごみの減量が進むと予想される中、廃棄物を安定的・効率的に処理するためには広域的な施設整備の検討が必要であること、3市2町はいずれも現行のごみ処理施設の更新時期が近付いていることなどから、令和5年(2023年)5月、一般廃棄物処理に係る広域的な連携の取り組みを推進することを目的に、市町主導により担当課職員を構成員とする「ごみ処理広域化等連絡会」を設置しました。
ごみ処理広域化等連絡会では、令和6年度(2024年度)に、一般廃棄物処理施設広域化実現可能性調査を実施し、ごみ処理広域化・施設の集約化により得られる効果及び課題の調査、検討を行い、広域化の実現に向けて協議を進めています。
| 令和4年3月 | 静岡県が「静岡県一般廃棄物処理広域化マスタープラン」を策定 ・3市2町の枠組みが示され、経済面、環境面において現状より効果が高く、当面目指すものとして評価。 |
| 令和4年度 | 県主催「東部地域におけるごみ処理広域化・ごみ処理施設集約化に係る検討会」(全4回)(県、3市2町) |
| 令和5年5月 | 「ごみ処理広域化等連絡会」設置 ・構成:3 市 2 町の担当課職員 ・令和7年1月現在、合計11回開催 ・オブザーバーとして県担当職員も出席 |
| 令和6年5月 | 一般廃棄物処理施設広域化実現可能性調査(~10月) ・ごみ処理広域化・施設集約化により得られる効果及び課題の調査、整理 |

ごみ処理広域化の必要性
3市2町は、いずれも現行のごみ処理施設の更新時期が近付いており、施設の更新が共通の課題となっています。
また、人口減少やリサイクルなどの取り組みが進み、将来的にごみの減量が進むと予想される中、各市町が規模の小さいごみ処理施設を整備して運営するより、ごみ処理を広域化し、施設を集約化することで、施設建設費の抑制、電気や熱として回収するごみエネルギーの利活用、施設の運営、人材確保など、様々な面で効率的で安定的な運用が図られる可能性があることから、広域化の検討を進める必要があります。
 三島市清掃センターのごみ処理施設は、平成元年度(1989年度)の施設稼働から35年以上が経過し、老朽化が進行しています。特にごみ焼却処理施設は、平成12~13年度(2000~2001年度)にダイオキシン恒久対策整備による主要な設備の更新を図りましたが、焼却炉は900℃という高温にさらされる施設であるため機器設備の損耗が激しく、平成25~27年度(2013~2015年度)には、3か年をかけて基幹的設備整備工事を実施しています。
三島市清掃センターのごみ処理施設は、平成元年度(1989年度)の施設稼働から35年以上が経過し、老朽化が進行しています。特にごみ焼却処理施設は、平成12~13年度(2000~2001年度)にダイオキシン恒久対策整備による主要な設備の更新を図りましたが、焼却炉は900℃という高温にさらされる施設であるため機器設備の損耗が激しく、平成25~27年度(2013~2015年度)には、3か年をかけて基幹的設備整備工事を実施しています。
また、平成28年度(2016年度)からは、2炉の焼却炉のうち1炉のみを24時間連続運転することで、電力・燃料の削減を図るとともに、設備の負担を軽減しています。それでも、基幹的設備以外の機器等は設置当時のままであり、予算の制約がある中、定期的な清掃点検と緊急度を優先した修繕を実施しながら、安定したごみ焼却処理機能の確保を図っている状況です。
このような施設・設備の維持管理や負担軽減の工夫、さらには市民のごみの減量化が進んでいる状況の中で、清掃センターの個別施設計画においては、焼却施設、粗大ごみ処理施設ともに、令和17年度までを目標に延命化を図ることとしています。
また、人口減少やリサイクルなどの取り組みが進み、将来的にごみの減量が進むと予想される中、各市町が規模の小さいごみ処理施設を整備して運営するより、ごみ処理を広域化し、施設を集約化することで、施設建設費の抑制、電気や熱として回収するごみエネルギーの利活用、施設の運営、人材確保など、様々な面で効率的で安定的な運用が図られる可能性があることから、広域化の検討を進める必要があります。
三島市の現行施設の状況

また、平成28年度(2016年度)からは、2炉の焼却炉のうち1炉のみを24時間連続運転することで、電力・燃料の削減を図るとともに、設備の負担を軽減しています。それでも、基幹的設備以外の機器等は設置当時のままであり、予算の制約がある中、定期的な清掃点検と緊急度を優先した修繕を実施しながら、安定したごみ焼却処理機能の確保を図っている状況です。
このような施設・設備の維持管理や負担軽減の工夫、さらには市民のごみの減量化が進んでいる状況の中で、清掃センターの個別施設計画においては、焼却施設、粗大ごみ処理施設ともに、令和17年度までを目標に延命化を図ることとしています。
| 平成元年度 | ごみ焼却施設稼働開始 粗大ごみ処理施設稼働開始 |
| 平成9年度 | 全連続燃焼式に変更 処理能力180t/日(90t(24h)×2炉) |
| 平成12年度 | ダイオキシン恒久対策事業(~平成13年) |
| 平成25年度 | ごみ焼却施設基幹的設備整備工事(~平成27年度) 粗大ごみ処理施設基幹的設備整備工事(25年度、28年度) |
一般廃棄物処理施設広域化実現可能性調査
本調査は、令和6年度(2024年度)、3市2町の一般廃棄物処理状況、施設整備状況及び地理的状況等を踏まえ、ごみ処理広域化・施設集約化により得られる効果と課題を調査し、広域化の実現可能性を判断する基礎資料として取りまとめたものです。
収集運搬距離の延伸、現状で市町により異なる分別区分の整理、広域処理するごみの種類とそれに応じて整備すべきごみ処理施設、広域連携の組織体制など、広域化に向けて検討すべき項目の洗い出しを行う一方、3市2町で広域化した場合は、単独整備した場合と比較して、建設費及び運営管理費において各市町の負担額が減少すると試算されました。
(3)処理フロー (4)費用負担 (5)分別区分・有料化
(6)収集運搬 (7)過渡期の処理方法 (8)スケジュール
収集運搬距離の延伸、現状で市町により異なる分別区分の整理、広域処理するごみの種類とそれに応じて整備すべきごみ処理施設、広域連携の組織体制など、広域化に向けて検討すべき項目の洗い出しを行う一方、3市2町で広域化した場合は、単独整備した場合と比較して、建設費及び運営管理費において各市町の負担額が減少すると試算されました。
【検討事項】
(1)組織体制 (2)整備する一般廃棄物処理施設(3)処理フロー (4)費用負担 (5)分別区分・有料化
(6)収集運搬 (7)過渡期の処理方法 (8)スケジュール
- 一般廃棄物処理施設広域化実現可能性調査(令和6年(2024年)10月)
- 一般廃棄物処理施設広域化実現可能性調査概要版(同上)
これからの取り組み
3市2町は、「一般廃棄物処理施設広域化実現可能性調査」の結果を踏まえ、引き続き連携してごみ処理広域化の検討を進めていくため、副市長・副町長を構成員とする「ごみ処理広域化検討協議会」を新たに設置することになりました。
- 3市2町は、副市長及び副町長を構成員とする「ごみ処理広域化検討協議会」を新たに立ち上げ、ごみ処理広域化の検討を進めていきます。
- 協議会では、令和7年度(2025年度)から、3市2町の地域内で建設候補地の選定に向けた検討を行います。
- 令和7年度(2025年度)は、協議会での検討に向け、3市2町の共同で建設候補地選定委員会(委員:学識経験者、市町職員)を設置します。
- 各市町は、公有地等からの抽出による方法又は各市町の公募による方法により建設候補地を選出し、選定委員会における評価検討の結果を踏まえ、今後広域化に参加するか否かを判断します。
| 令和6年度 | 第1回ごみ処理広域化検討協議会(令和7年3月開催予定) |
| 令和7年度~ | 一般廃棄物処理施設建設候補地選定の検討 (建設候補地選定委員会の設置、建設候補地選定支援業務委託、候補地の公募、等) |
| 令和8年度 | 各市町にて、広域化へ参加の可否の判断 |