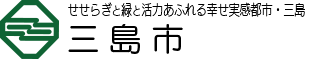三島市 指定等文化財を紹介します(国指定 その1)
三島市の指定等文化財についてお知らせします。
三島市の指定等文化財
三島市には令和6年(2024)4月現在、95件の指定等文化財があります。そのうち国指定は25件、県指定は13件、市指定は48件、また、9件の建造物が国登録文化財となっています。
これらの文化財について、紹介します。
(指定文化財紹介ページの移行中のため、一部の情報が未掲載となりますが、順次追加していきます。)
(指定文化財紹介ページの移行中のため、一部の情報が未掲載となりますが、順次追加していきます。)
三嶋大社本殿、幣殿及び拝殿
種別 国指定、重要文化財(建造物)
よみ みしまたいしゃほんでん、へいでん および はいでん
員数 1棟
所有者・管理者 三嶋大社
所在地 大宮町
指定日 平成12年5月25日
概要
本殿、幣殿及び拝殿は流造の本殿と入母屋造の拝殿を両流造の幣殿で繋いだ複合社殿の形式である。現存するのは安政元年(1854)の東海大地震後に再建されたもので、神主矢田部盛治が全国に再建のための勧進を行い、慶応2年(1866)に落成した。境内のその他の建築物も明治元年には再建されている。その後の修理等で床や建具など一部に変更はあるが、諸記録や痕跡から旧規は明らかである。
本殿妻飾や幣殿・拝殿接合部など、各部の形式や細工に趣向を凝らしている。また、上質な欅を用い、素木の美しさと要所に彫刻を配した華やかさを具備している。江戸時代末期の装飾豊かな複合社殿建築として高い価値がある。

三嶋大社本殿、幣殿および拝殿(後方の建造物)
よみ みしまたいしゃほんでん、へいでん および はいでん
員数 1棟
所有者・管理者 三嶋大社
所在地 大宮町
指定日 平成12年5月25日
概要
本殿、幣殿及び拝殿は流造の本殿と入母屋造の拝殿を両流造の幣殿で繋いだ複合社殿の形式である。現存するのは安政元年(1854)の東海大地震後に再建されたもので、神主矢田部盛治が全国に再建のための勧進を行い、慶応2年(1866)に落成した。境内のその他の建築物も明治元年には再建されている。その後の修理等で床や建具など一部に変更はあるが、諸記録や痕跡から旧規は明らかである。
本殿妻飾や幣殿・拝殿接合部など、各部の形式や細工に趣向を凝らしている。また、上質な欅を用い、素木の美しさと要所に彫刻を配した華やかさを具備している。江戸時代末期の装飾豊かな複合社殿建築として高い価値がある。

三嶋大社本殿、幣殿および拝殿(後方の建造物)
絹本著色日蓮上人像
種別 国指定、重要文化財(絵画)
よみ けんぽんちゃくしょく にちれんしょうにんぞう
員数 1幅
所有者・管理者 妙法華寺
所在地 玉沢
指定日 大正8年8月8日
概要
鎌倉時代末期の作。 日蓮上人・本尊・壇具・武家夫妻が描かれている。絹地に細かい截金、朱、群青、緑青、肌色など謹厳な墨描きとともに鎌倉時代仏画の特色をよく示している。全体に古色を呈しているが、なお美しさと荘厳さを保っている。作者は日蓮に随身した画家、大蔵卿であると伝えられる。

よみ けんぽんちゃくしょく にちれんしょうにんぞう
員数 1幅
所有者・管理者 妙法華寺
所在地 玉沢
指定日 大正8年8月8日
概要
鎌倉時代末期の作。 日蓮上人・本尊・壇具・武家夫妻が描かれている。絹地に細かい截金、朱、群青、緑青、肌色など謹厳な墨描きとともに鎌倉時代仏画の特色をよく示している。全体に古色を呈しているが、なお美しさと荘厳さを保っている。作者は日蓮に随身した画家、大蔵卿であると伝えられる。

絹本著色十界勧請大曼荼羅図(絵曼荼羅)
種別 国指定、重要文化財(絵画)
よみ けんぽんちゃくしょく じっかいかんじょうだいまんだらず(えまんだら)
員数 1幅
所有者・管理者 妙法華寺
所在地 玉沢
指定日 大正9年4月15日
概要
本図は鎌倉時代末期の作と推測され、日蓮が佐渡へ流されている折の創意による作と伝えられる。この絵曼荼羅は中央上部に「南無妙法蓮華経」の題目を大書し、左右に諸仏や諸菩薩、下部に高僧、武士、日蓮等を描いている。全体に焼けて暗色になっているが、細緻な截金、群青、緑青など美しい色彩も残っており、鎌倉仏画の作例として貴重である。

よみ けんぽんちゃくしょく じっかいかんじょうだいまんだらず(えまんだら)
員数 1幅
所有者・管理者 妙法華寺
所在地 玉沢
指定日 大正9年4月15日
概要
本図は鎌倉時代末期の作と推測され、日蓮が佐渡へ流されている折の創意による作と伝えられる。この絵曼荼羅は中央上部に「南無妙法蓮華経」の題目を大書し、左右に諸仏や諸菩薩、下部に高僧、武士、日蓮等を描いている。全体に焼けて暗色になっているが、細緻な截金、群青、緑青など美しい色彩も残っており、鎌倉仏画の作例として貴重である。

木造大日如来坐像
種別 国指定、重要文化財(彫刻)
よみ もくぞうだいにちにょらいざぞう
員数 1躯
所有者・管理者 佐野美術館
所在地 中田町
指定日 明治32年8月8日
概要
高 92.2 cm、平安時代(12世紀)
大日如来は、密教で世界の中心にいると考えられている仏である。その世界の表現方法として、全体の仕組みを表す「金剛界」と、構成する仏たちの役割を示す「胎蔵界」とがあり、それぞれ仏の形が少しずつ異なる。この像は左人差し指を右手で握る智拳印を結んでいて、金剛界の大日如来であることがわかる。半眼で穏やかな表情、丸みを帯び均整のとれた体躯、このような仏像の姿を「定朝様式」といい、平安時代に京の都を中心に流行した。本像は大阪府河内長野市の河合寺にあり、周辺地域にも都の流行が伝わっていたことがわかる。
(参考 佐野美術館HP)

よみ もくぞうだいにちにょらいざぞう
員数 1躯
所有者・管理者 佐野美術館
所在地 中田町
指定日 明治32年8月8日
概要
高 92.2 cm、平安時代(12世紀)
大日如来は、密教で世界の中心にいると考えられている仏である。その世界の表現方法として、全体の仕組みを表す「金剛界」と、構成する仏たちの役割を示す「胎蔵界」とがあり、それぞれ仏の形が少しずつ異なる。この像は左人差し指を右手で握る智拳印を結んでいて、金剛界の大日如来であることがわかる。半眼で穏やかな表情、丸みを帯び均整のとれた体躯、このような仏像の姿を「定朝様式」といい、平安時代に京の都を中心に流行した。本像は大阪府河内長野市の河合寺にあり、周辺地域にも都の流行が伝わっていたことがわかる。
(参考 佐野美術館HP)

梅蒔絵手箱
種別 国指定、国宝(工芸品)
よみ うめまきえてばこ
員数 1具
所有者・管理者 三嶋大社
所在地 大宮町
指定日 昭和27年11月22日
概要
源頼朝の妻政子が奉納したと伝えられる手箱。この手箱には化粧道具一式34点が納められ、鎌倉時代の代表的な蒔絵の工芸品で、咲きほこる梅花と飛翔する雁が描かれており、当時の上層階級の風雅が偲ばれる。 現在は東京国立博物館に寄託されている。

よみ うめまきえてばこ
員数 1具
所有者・管理者 三嶋大社
所在地 大宮町
指定日 昭和27年11月22日
概要
源頼朝の妻政子が奉納したと伝えられる手箱。この手箱には化粧道具一式34点が納められ、鎌倉時代の代表的な蒔絵の工芸品で、咲きほこる梅花と飛翔する雁が描かれており、当時の上層階級の風雅が偲ばれる。 現在は東京国立博物館に寄託されている。

薙刀 銘備前国長船住人長光造
種別 国指定、国宝(工芸品)
よみ なぎなた めいびぜんのくにおさふねじゅうにんながみつつくる
員数 1口
所有者・管理者 佐野美術館
所在地 中田町
指定日 昭和32年2月19日
概要
刃長 44.2 cm、反り 1.7 cmを測る。
長光は鎌倉時代を代表する備前長船(現在の岡山県)の刀工。長船派の祖・光忠の子で、大工房の長として活躍し、同時代では在銘作が最も多く残る刀工である。作風は、父親に似た 華やかな丁子乱れの作から、変化の少ない互の目調のものまで多様である。
薙刀は、鎌倉時代から室町時代にかけて実戦で使われた消耗品であるため、本品のように保存状態がよいものは非常に珍しい。津山松平家に伝来した。昭和63 年(1988)佐藤寛次氏より寄贈。
(参考 佐野美術館HP)

よみ なぎなた めいびぜんのくにおさふねじゅうにんながみつつくる
員数 1口
所有者・管理者 佐野美術館
所在地 中田町
指定日 昭和32年2月19日
概要
刃長 44.2 cm、反り 1.7 cmを測る。
長光は鎌倉時代を代表する備前長船(現在の岡山県)の刀工。長船派の祖・光忠の子で、大工房の長として活躍し、同時代では在銘作が最も多く残る刀工である。作風は、父親に似た 華やかな丁子乱れの作から、変化の少ない互の目調のものまで多様である。
薙刀は、鎌倉時代から室町時代にかけて実戦で使われた消耗品であるため、本品のように保存状態がよいものは非常に珍しい。津山松平家に伝来した。昭和63 年(1988)佐藤寛次氏より寄贈。
(参考 佐野美術館HP)

短刀 表ニ三島大明神他人不与之/裏ニ貞治三年藤原友行
種別 国指定、重要文化財(工芸品)
よみ たんとう おもてに みしまだいみょうじん たのひとにこれをあたえず/うらに じょうじさんねんふじわらともゆきの めいあり
員数 1口
所有者・管理者 三嶋大社
所在地 大宮町
指定日 明治44年4月17日
概要
南北朝時代の貞治3年(1364)、藤原友行によるもので、長さ34.8cm。
よみ たんとう おもてに みしまだいみょうじん たのひとにこれをあたえず/うらに じょうじさんねんふじわらともゆきの めいあり
員数 1口
所有者・管理者 三嶋大社
所在地 大宮町
指定日 明治44年4月17日
概要
南北朝時代の貞治3年(1364)、藤原友行によるもので、長さ34.8cm。
太刀 銘宗忠
種別 国指定、重要文化財(工芸品)
よみ めいむねただ
員数 1口
所有者・管理者 三嶋大社
所在地 大宮町
指定日 明治45年2月8日
概要
鎌倉時代の太刀で、刃長81.8cm、表に「宗忠」の銘がある。明治20年、明治天皇より奉納されたものである。宗忠は鎌倉時代初期、備前福岡一文字派の名工である。 この太刀は平安時代の風調を残し、流麗な反りに気品がただよう。地鉄は澄んで備前特有の淡い映りが立ち、刃文は小丁文字で初期福岡一文字の典型的作風を表した優品である。

よみ めいむねただ
員数 1口
所有者・管理者 三嶋大社
所在地 大宮町
指定日 明治45年2月8日
概要
鎌倉時代の太刀で、刃長81.8cm、表に「宗忠」の銘がある。明治20年、明治天皇より奉納されたものである。宗忠は鎌倉時代初期、備前福岡一文字派の名工である。 この太刀は平安時代の風調を残し、流麗な反りに気品がただよう。地鉄は澄んで備前特有の淡い映りが立ち、刃文は小丁文字で初期福岡一文字の典型的作風を表した優品である。