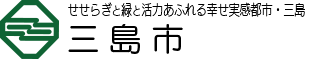戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求について
第十二回特別弔慰金について現在受付準備中です。
受付開始に向け現在準備中です。
受付開始は令和7年5月上旬を予定しています。
受付開始は令和7年5月上旬を予定しています。
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、戦没者等の死亡当時のご遺族で、次の順番による最も先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1 弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の (1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等との生計関係の有無や、ご遺族の婚姻・養子縁組の状況によって、同じ立場であっても順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の 戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を有していた方に限ります。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1 弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の (1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等との生計関係の有無や、ご遺族の婚姻・養子縁組の状況によって、同じ立場であっても順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の 戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5000円、5年償還の記名国債
※国債の償還金は令和8年から毎年1回償還日以降に、年5万5000円ずつ支払いを受けることができます。
※国債の償還金は令和8年から毎年1回償還日以降に、年5万5000円ずつ支払いを受けることができます。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
三島市役所での受付開始は令和7年5月上旬を予定しています。
※請求期間内に請求を行わない場合、第十ニ回特別弔慰金を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※昨今の社会情勢等により、請求書の受付から国債の交付までは、概ね半年以上(ピーク時は1年以上)かかっています。
三島市役所での受付開始は令和7年5月上旬を予定しています。
※請求期間内に請求を行わない場合、第十ニ回特別弔慰金を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※昨今の社会情勢等により、請求書の受付から国債の交付までは、概ね半年以上(ピーク時は1年以上)かかっています。
請求窓口
・請求者の住所地を管轄する市区町村窓口(福祉総務課)
・成年後見人等や相続人の場合は、その成年後見人等や相続人の住所地を管轄する市区町村
・単なる請求手続きの代理人(受任者)の場合は、請求書の住所地で受付けます。
・前回の特別弔慰金受給者は、前回の裁定通知書をお持ちいただくと窓口での受付が比較的スムーズに進みます。
・成年後見人等や相続人の場合は、その成年後見人等や相続人の住所地を管轄する市区町村
・単なる請求手続きの代理人(受任者)の場合は、請求書の住所地で受付けます。
・前回の特別弔慰金受給者は、前回の裁定通知書をお持ちいただくと窓口での受付が比較的スムーズに進みます。
請求受付時間
平日(月曜日~金曜日):9時~11時30分、13時~16時
○書類の確認等に時間を要することが想定されますので、お時間に余裕を持ってご来庁ください。
○状況によっては、一度のご来庁では事務手続きが終了しないこともございますのでご了承ください。
○土曜日・日曜日・祝日等の市役所閉庁日は、受付を行いませんのでご了承ください。
○書類の確認等に時間を要することが想定されますので、お時間に余裕を持ってご来庁ください。
○状況によっては、一度のご来庁では事務手続きが終了しないこともございますのでご了承ください。
○土曜日・日曜日・祝日等の市役所閉庁日は、受付を行いませんのでご了承ください。
請求に必要な主な書類等
1.前回の特別弔慰金受給者(継続請求)が請求する場合
【前回の受給者本人(配偶者以外)】
(1)請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書等)
(2)請求書《福祉総務課に様式あり》
(3)遺族の現況等申立書《福祉総務課に様式あり》
(4)請求者の戸籍《令和7年4月1日以降のもの》
【前回の受給者本人(配偶者)】
上記の(1)~(4)の書類に加えて
(5)特別弔慰金失権事由非該当申立書《福祉総務課に様式あり》
(6)前回受給の特別弔慰金の基準日から令和7年3月31日の間の戸籍
2.継続請求で前回受給者以外が請求する場合
1.の(1)~(4)の書類に加えて
(7)戦没者死亡当時における戦没者と請求者との続柄を証する戸籍
(8)先順位者がいないことを証する戸籍《該当者のみ》
(9)戦没者の死亡当時から令和7年3月31日の間の請求者の戸籍《該当者のみ》
(10)「生計関係申立書」及び「1年以上生計関係を有していたことがわかる資料」《該当者のみ》
※特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。
3.新規に請求する場合(請求権はあったが請求していない者を含む)
1.(1)~(6)、2.(7)~(10)の書類に加えて
(11)年金給付の受給権者がいないことを証する戸籍
4.その他、請求者の状況に応じて必要となる書類
【成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)が請求する場合】
1.(1)~(6)、2.(7)~(10)、3.(11)のうち該当する書類に加えて
(12)法務局の登記事項証明書等
【相続人が請求する場合】
1.(1)~(6)、2.(7)~(10)、3.(11)のうち該当する書類に加えて
(13)相続人であることを証する戸籍等
ア:被相続人が基準日以降に死亡していることを確認できる戸籍
イ:請求者(相続人)の請求時の戸籍
ウ:相続人と被相続人との続柄が分かる戸籍
※改姓等をしている場合は、2項目(名と生年月日等)以上の一致でイ・ウに記載されているものが同一人物 であると確認できること
エ:請求者より民法上先順位者がいないことが確認できる戸籍
【外国居住のため代理人が請求する場合】
1.(1)~(6)、2.(7)~(10)、3.(11)のうち該当する書類に加えて
(14)委任状《福祉総務課に様式あり》
【請求者が高齢である等、市役所で手続きすることができない場合】
1.(1)~(6)、2.(7)~(10)、3.(11)のうち該当する書類に加えて
(14)委任状《福祉総務課に様式あり》
※受任者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を提示してください。
記載時の注意事項
黒色のボールペンで記載してください。消すことができる鉛筆やフリクションペンは使用できません。
請求書には、バーコードがついているため、コピーして使うことはできません。
前回受給者と今回請求者が同一で前回の現況等申立書のコピーを保管している場合、コピーに追記・署名して提出することができます。
【遺族の氏名】
○戦没者死亡当時の三親等内親族の、令和7年4月1日現在の氏名及び生年月日を記載してください。
○婚姻等で姓が変わった場合は、改姓後の姓で記載してください。
【続柄】
○戦没者からみた続柄を記載してください。・・・「妻」「子」「妹」など
【遺族の令和7年3月31日までの状況】
○死亡等の年月日は必ず記入してください。
○戦没者の妻が遺族外再婚により失権した場合も記載してください。
○婚姻の場合、改氏婚かどうか分かるように記載してください。
○失権事由の「離縁」は養子縁組の解消を指します。
○先順位者及び年金受給権者(父母・祖父母)の死亡について、国内最高齢者(男性:大正3年3月14日、女性:明治42年9月2日)より前の場合、戸籍の提出は不要です。
○《請求に必要な主な書類等》に記載した戸籍の取得は、「市民課」へお問い合わせください。
1.(2)特別弔慰金請求書
請求書には、バーコードがついているため、コピーして使うことはできません。
1.(3)現況等申立書
前回受給者と今回請求者が同一で前回の現況等申立書のコピーを保管している場合、コピーに追記・署名して提出することができます。
【遺族の氏名】
○戦没者死亡当時の三親等内親族の、令和7年4月1日現在の氏名及び生年月日を記載してください。
○婚姻等で姓が変わった場合は、改姓後の姓で記載してください。
【続柄】
○戦没者からみた続柄を記載してください。・・・「妻」「子」「妹」など
【遺族の令和7年3月31日までの状況】
○死亡等の年月日は必ず記入してください。
○戦没者の妻が遺族外再婚により失権した場合も記載してください。
○婚姻の場合、改氏婚かどうか分かるように記載してください。
○失権事由の「離縁」は養子縁組の解消を指します。
戸籍書類
○先順位者及び年金受給権者(父母・祖父母)の死亡について、国内最高齢者(男性:大正3年3月14日、女性:明治42年9月2日)より前の場合、戸籍の提出は不要です。
○《請求に必要な主な書類等》に記載した戸籍の取得は、「市民課」へお問い合わせください。
国債のお渡しについて
○請求書類は市区町村で受付をした後、静岡県又は戦没者の本籍地である都道府県において審査されます。この都道府県の審査・裁定(可決)に基づいて、国が国債を交付し、国債は請求受付をした市区町村を通じて請求者にお渡しすることになります。
○昨今の社会情勢等により、請求書の受付から国債の交付までは、概ね半年以上(ピーク時は1年以上)かかっています。
○特別弔慰金を過去に一度も請求されたことがない場合や、前回受給者から請求者が変更されている場合、また、審査裁定を行う都道府県(戦没者の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住地都道府県が異なるときには、さらに時間がかかる場合がありますので、予めご承知おきください。
○昨今の社会情勢等により、請求書の受付から国債の交付までは、概ね半年以上(ピーク時は1年以上)かかっています。
○特別弔慰金を過去に一度も請求されたことがない場合や、前回受給者から請求者が変更されている場合、また、審査裁定を行う都道府県(戦没者の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住地都道府県が異なるときには、さらに時間がかかる場合がありますので、予めご承知おきください。