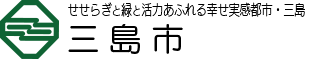三島市新庁舎整備基本構想(案)へのご意見と、それに対する市の考え方
| 該当箇所 | 意見の概要 | 市の考え方 | 反映結果 |
|---|---|---|---|
| 三島市新庁舎整備基本構想(案) | 新庁舎は、三島市民に行政サービスを提供する機関の中枢になる建物であり、三島市民は、この建物をよりどころとして社会生活を営み、継続する大切な建物です。そのため市職員や一部市民の過剰な要望を取り入れて三島市の現状に不釣り合いな市庁舎を建設しても、これからの社会情勢がどのように変化し、どれだけの税収入があるのか不透明な現状を鑑みると過剰で華美な庁舎は立てられません。三島市民に適合した規模の建物を建設してほしいものです。 現在は、市庁舎を建設する場所だけを検討材料にしているように見えますが、そもそも三島市には、将来にわたる都市計画があるようには思えません。三島市をどのような街にするのか全体像の絵が描き切れていないまま無計画に市庁舎建設事業を進めているように見え、その計画自体、市の行う事業の一つ一つがその場しのぎのプロパガンダ的な事業対応で市政は進んでいるように思えます。 又、市が行う一般行政手続きは、今はできなくてもすべてがAI化できるようになります。先を見通して市の行政事務、財政、人口減少も考慮し経済的にも維持管理できるような庁舎を建設すべきです。 三島市は、市庁舎建設資金として政府や県の交付金や補助金を考慮しているようですが、政府等の方針、政策の変更により減額又は未交付とされ、三島市の財政負担が予定より多額となる可能性もあると思います。三島市はインフラ整備に対する投資が進んでおらず、現在進行中の三島駅南口再開発事業、その他ゴミ処理場の建設等大きなインフラ整備事業を行う必要性が目白押しで、市民の税負担は多額で高額となります、三島市は地理的にも経済的にもこれ以上の経済的発展を見込むことは困難であることから、将来の市民に過剰な負担を残さず、笑われないような身の丈に合った合理的な新庁舎の建設をお願いします。 |
新庁舎の規模に関しては、基本構想(案)の36~41ページに記載の通り、人口減少やライフサイクルコストを考慮し、現状の総延べ床面積15,789㎡よりも小規模となる13,234㎡を目標としております。 また、基本構想(案)の31ページでお示ししているように、長期使用への配慮や施設の可変性も考慮する中で、事業を進めていきます。 市民皆様へのご負担については、ファシリティマネジメントの考え方に基づき、将来の財政負担の軽減を図っていきます。 |
既に盛り込み済のもの |
| 三島市新庁舎整備基本構想(案) 5ページ 6行目 | 新庁舎の基本的な説明をお願いします。 1)いつから新庁舎候補地が北田町と二日町の2択になったのか? 2)北田町と二日町以外の候補地は何処だったのか? パブコメ以前の問題ですが、回答ヨロシクお願い致します。 |
1)基本構想(案)の63ページに記載の通り、平成27年9月から検討を始め、令和3年3月の市民会議検討成果報告書などを踏まえたうえで2つの候補地に絞り、検討を進めることとなりました。 なお、63ページについては見易くなるように、内容を一部修正しました。 2)別添資料の21ページに記載の通り、北田町と南二日町以外では、「南田町広場」、「三島駅南口」、「中央町別館と周辺民有地」、「生涯学習センター、市民文化会館、学校施設などの大規模改修」の候補もありましたが、敷地の規模や費用面、事業スケジュールの相違等から、2つの候補地に絞られていきました。 |
政策案に反映したもの(一部反映を含む) |
| 三島市新庁舎整備基本構想(案) 6ページ 1行目 | 以前の基本構想には、市役所に行く必要のない市役所、というコンセプトがありましたが、この新構想では無くなっています。今後、コンビニなどでICT技術を活用することにより、正に、市役所に行く必要のない市役所、が実現出来ていくと思いますし、それが市民にとっての利便性向上に寄与すると思います。何故、当初あったコンセプトを削除したのですか? | 当初は「三島市スマート市役所宣言」(令和元年12 月宣言)に基づき、新庁舎のコンセプトを"市役所に来る必要がない市役所"としていましたが、令和5年7月に「三島市DX推進計画」が策定され、" 誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化"(デジタルデバイドの解消)がビジョンの1つとして示されました。 見直した理由としましては、デジタル化が進んだとしても市役所にお越しいただく方が一定数いらっしゃることから、「三島市DX推進計画」のビジョンに基づき、基本構想(案)の32ページに記載の通り、誤解が生じないような表現に改めることとしました。 |
その他(質問など) |
| 三島市新庁舎整備基本構想(案) 2行目 | 1) 現在の市役所が分散していることを課題としていますが、以前の市民アンケートでは、確か、9割ほどの市民が市役所本庁を利用していると回答していました。つまり、市役所が分散していることによる不便を実際に経験している市民は極めて少数だと思いますが如何でしょうか? 2) Q3の意見とも関連しますが、市役所機能を一つの場所に集約して、そこに市民に来てくれという発想自体を変えるべきだと思います。今後、証明書などの発行業務はどんどんコンビニなどで代替されていくと思います。市役所が果たすべき市民サービスは市民に寄り添うコンサル的なものが中心になっていくと思います。よって、一箇所集中ではなく、出来るだけ市民の住まいの近くにある公民館などの公共施設に市役所機能を分散するべきです。どうでしょうか? |
1)分散化の課題については、「市議会公共施設等マネジメント検討特別委員会調査報告書」(基本構想(案)19ページ)、「庁舎に関する市民アンケート調査」(基本構想(案)21ページ)、「市議会報告会における市民からの要望」(基本構想(案)23ページ)、などをもとに、市民の利便性や事務の効率化を図る観点から、新庁舎においては統合する方針としています。 2)市役所機能の分散については、別添資料の19~20ページに記載の通り、庁舎と公民館などの出先施設をネットワークでつなぐことで、最寄りの施設から様々な手続きを可能とする、いわゆるサテライト市役所によるサービスの提供についての調査研究を進めていく考えでいます。 |
今後の参考とするもの |
| 三島市新庁舎整備基本構想(案) 17行目 | 十分な駐車場の確保、という市民要望が書かれています。一方で、頻繁に市役所を訪れる市民は10%もいません(市民アンケートの結果から90%以上は3ケ月に1回又はそれより低い頻度)。Q3とも関連しますが、今後、益々市役所に出向かなくてはいけない必要性は減っていきます。こういう状況にもかかわらず駐車場の規模確保にこだわる理由がわかりません。何故でしょうか? | 基本構想(案)の22ページに記載の通り、市民アンケート調査の結果において、70%以上の市民が自家用車で来庁しているうえ、60%以上の市民が駐車場の使い勝手に困っているとの回答を得ていますので、十分な駐車場の確保が必要であると捉えています。 また、基本構想(案)の42~46ページに記載の通り、令和13年度の供用開始時の駐車場台数においては、現状の総数から17台を増やした240台を目標としていますが、その後の社会情勢の変化等に伴い、将来的には駐車場敷地の一部を別用途に変更するなどして83台を減らし、157 台とする方向性で検討を進めていきます。 |
既に盛り込み済のもの |
| 三島市新庁舎整備基本構想(案) 図表11-2 | 11/26の岡田議員の一般質問で、三島二日町駅周辺等の道路整備が取り上げられました。新庁舎を南二日町にする場合、混雑緩和の為の道路整備が必須かと思われます。この費用も新庁舎整備の概算に含めるべきだと思いますが含まれているのでしょうか?含まれていないのならその理由は何故でしょうか? | 南二日町広場案の概算事業費については、約105.8億円となっておりますが、この費用の中においては、国道1号への接続、敷地内道路、旧下田街道丁字路の整備費を既に見込んでおります。 混雑緩和のための道路整備費については、新庁舎整備に伴う交通量の変化や将来予測、対策の検討などが現段階では非常に困難であることから費用の算出は、両候補地ともに行えておりません。 また、ご指摘の内容については、現状における対策ともなりますので、道路行政におけるインフラ整備として、新庁舎整備事業とは異なる事業にて、検討してまいります。 |
その他(質問など) |
| 三島市新庁舎整備基本構想(案) 図16-2 | 南二日町に新庁舎を建設する場合の現庁舎等の跡地利用の方針が非常に曖昧模糊としているように感じます。まちなかの賑わい創出を謳ってますが本当に実現できるのでしょうか?民間活力の導入が基本とありますが、税金の投入は無し、と考えていいですか? | 基本構想(案)の61ページに記載の通り、シミュレーション結果において、公共施設よりも民間施設の方が、人の動きに増加傾向が見られたことから、民間活力の導入が望ましいものととらえております。 今後においては、まちなかの更なる魅力と賑わいの創出に向けて、現状の様々な計画などを勘案しながら、どのような施設が望ましいのか、検討を進めていきます。 なお、検討を進めるにあたりましては、商工会議所や観光協会、商店街連盟などにもご意見を伺うとともに、民間事業者からの市場調査を行うなどして、実現に向けて取り組んでまいります。 |
その他(質問など) |
| 三島市新庁舎整備基本構想(案) 33ページ 6-8行目 | 大規模災害時等とあるが、国民保護の観点がないように思えるため、組み込む必要があると考えます。 Jアラートの訓練をしているのにも関わらず、これから建設する新庁舎にそういった機能を想定してないのでは、市国民保護計画が果たせないのではないかと思います。また、電磁パルスによりあらゆる電子機器が使えなくなった場合の想定も必要であると考えます。 |
基本構想(案)の34ページに記載の通り、有事の際にも電力や通信、給水、排水などのインフラ機能を可能な限り確保できるように努めていきます。 また、電磁パルスに関しては、国の動向などを確認しつつ、今後の参考とさせていただきます。 |
今後の参考とするもの |
| 三島市新庁舎整備基本構想(案) 42ページ | 現庁舎跡地有効活用について 三島市財政は健全であることを伺ったため、しっかり資金繰りを行えば若い次世代の子女達に伝統、歴史、文化、と魅力ある街を残せます。売却する必要はありません。あえてするならば、賃貸とすること。また財政を豊かにするためには「ふるさと納税」を強力に推進する必要があります。 |
基本構想(案)の93ページに記載の通り、跡地については、公共施設等総合管理計画に基づき、原則売却としていますが、将来を見据える中でより有効な利活用が見込まれる土地は、民間活力の活用等、売却以外の手法も検討していきます。 また、ふるさと納税については、他自治体の好事例や取組も調査・研究しながら、意欲ある生産者や事業者、関係団体の皆様とともに、新たな返礼品の開発や有効なプロモーションの展開に努めていきます。 |
今後の参考とするもの |
| 三島市新庁舎整備基本構想(案) 64ページ 10行目 | 駐車場の確保と今後のまちづくりの方向 ・新庁舎の駐車場の規模は240台を想定している。この数は現状の駐車場の利用数(43ページ 表8-6に近い。市民アンケートの市役所の訪れる際の交通手段では75%が自動車となっている(43ページ表85)、次いで徒歩11%、自転車7%とあり、交通機関時に寄らない来庁が2割近くある。 現状の施設が市街地にあり、他の所要と併せて立ち寄るなどのアクセスが可能のためである。二日町広場の場合、住宅地ではあるが、商業施設や通行人は少なくなることから、この割合は少なくなるのでないか。 環境負荷の低減は「第5章 新庁舎整備の基本方針」の「施設の可能性」(31ページ)でシェアリングの普及、「基本機能の見直し」(32ページ)の「環境への配慮」で省資源等が挙げられている。現在ではアクセスの確保に自動車は必要であるが、今後のまちづくりの方向に車依存への抑制を持つことが必要であると考える。 |
基本構想(案)の43~46ページに記載の通り、駐車場台数の240台については、令和3 年度以降に新庁舎を供用開始または予定している全国50 自治体の自動車保有台数と庁舎駐車場台数との相関関係から算出しているため、庁舎の位置により大きく変動する値ではないと考えております。 将来的な駐車場台数については、今後の社会情勢の変化等に伴い、駐車場敷地の一部を別用途に変更するなどして、157 台とする方向性で検討を進めていきます。 |
反映できないもの |
| 三島市新庁舎整備基本構想(案) 86ページ 1行目 | 災害対策本部の機能の確保 ・浸水想定区域の建物はかさ上げで回避するとされている(65ページ10行目)。災害対策本部として機能するには周辺道路への接続が必要であるが、1号線への接続以外の周辺道路もかさ上げ等の対策はあるのか。 |
敷地の一部をかさ上げするとともに、国道1号への接続を図ることにより、浸水時の災害対応等も可能と捉えておりますことから、周辺道路のかさ上げ等の対策は検討しておりません。 | その他(質問など) |
| 三島市新庁舎整備基本構想(案)別添資料 142ページ 3-11行目 | 跡地利用の活用イメージ ・南二日町での整備として次世代モビリティの活用などをあげているが、都市部ではすでに使用が浸透している機能である。市街地からの自動車の抑制の方向は評価するが、市役所の機能の移動の必要性と結びつかない。さらに自動運転バスでの往復などは(11行目)移転、二日町広場のパークアンドライド利用は今後の跡地利用ではなく、現在のまちづくりの課題として取り組まれるべきではないか。 |
別添資料の49ページに関しては、跡地等を活用したまちづくりのイメージパターンの1例として記載しております。 まちづくりの対策については、まちなかの更なる魅力と賑わいを創出するために、別途検討することとしておりますので、いただいたご意見は今後の参考とさせていただきます。 |
今後の参考とするもの |
| 三島市新庁舎整備基本構想(案) 65ページ 6行目以降 | 概算金額とはいえ、建設費に100億円もかけないとならないのでしょうか。建設費が高騰しているのは理解していますが、コンサルの提案について、第3者機関による精査など行ってはいかがでしょうか? | 新庁舎整備の骨格を定める基本構想の策定段階においては、具体的な設計を行うものではないことから、事業費においても、現状況下での暫定的な面積や国の示す単価などから算出した概算額として捉えていただきたいと思います。 事業費の算出においては、今後策定する基本計画や基本設計、実施設計の中で、その都度、お示ししていくことを考えており、具体的な事項が段階ごとに定まってくることから、計画の節目ごとに金額の精度が高まっていくこととなります。 庁舎施設としての品質は確保しつつも、出来る限りのコスト削減を図るとともに、より多くの市民皆様が望むものとなるように努めてまいります。 また、第三者機関による精査については、必要に応じて、別添資料の40ページにあるCMr(コンストラクションマネージャー)の採用等の調査研究を進めていき、事業費の削減につなげていきたいと考えております。 |
既に盛り込み済のもの |
| 三島市新庁舎整備基本構想(案) 93ページ 9行目以降 | もともとの市庁舎や付属施設が三島の人々にとっては思い出や馴染みのある公共の空間であり、歴史的に見ても三島の重要な場所に位置していた施設跡地は、住宅利用でなく公共性のある利活用がよいのではないでしょうか?例えば公園にしたり、三島の新しい公的施設の候補地にするなど、検討できないでしょうか?将来の三島の地域資源となる土地を大切に扱えればと思います。 | 跡地活用のシミュレーションにおいては、公共施設よりも民間施設の方が、人の動きの増加傾向が見られたことから、民間活力の導入が望ましいものと捉えております。 また、基本構想(案)の93ページに記載の通り、跡地については、公共施設等総合管理計画に基づき、原則売却としていますが、将来を見据える中でより有効な利活用が見込まれる土地については、民間活力の活用等、売却以外の手法も検討していきます。 |
今後の参考とするもの |
| 三島市新庁舎整備基本構想(案) 7ページ 2-3行目 | 事務的には分散されていることが課題という見方は理解できますが、三島の環境としては分散していることは価値でもあると考えられます。 災害においては機能が分散されていることで、円滑に対応できる可能性も捨てられないかと思います。人口減少の時代でこれからの地方は経済的により困難になるので、拡大や大きな開発だけが発展とならず、環境をよくしたり、その環境や景観に馴染む施設をつくることが生活を豊かにすることも地域生活を豊かにするものと思えます。 一極集中の便利さもあると思いますが、別で記載したようにコストが高騰していることも考慮して、これまで三島ならではであった分散型市庁舎を再検討してもよいかと思いますが、いかがでしょうか? |
庁舎機能の集約化や他の公共施設の複合化については、来庁者の利便性や事務の効率化、円滑な災害対応の課題解決のほか、将来にわたる財政負担の軽減といったファシリティマネジメントの観点も踏まえた上で、「市議会公共施設等マネジメント検討特別委員会調査報告書」(基本構想(案)19ページ)や「庁舎に関する市民アンケート調査」(基本構想(案)21ページ)、「市議会報告会における市民からの要望」(基本構想(案)23ページ)などでいただいたご意見等も踏まえて検討を重ねた結果でありますのでご理解いただきたいと思います。 | 反映できないもの |